落語 厩火事
髪結いのお崎は亭主の八五郎とすぐに夫婦喧嘩になってしまう。
今日も喧嘩をしてご隠居のところに愚痴を言いに来た。
ご隠居:
「八五郎は道楽者だからよせといったのに おまえがどうしてもって一緒になったんだろう?いっそのこともう別れてしまいなさい」
お崎:
「それでもあの人にもいいところはあるんですよ」
けんかの愚痴を言いにきたくせに、ご隠居が突き放すとお崎は八五郎の弁護をはじめる始末
ただ八五郎の本心が知りたいとご隠居に訴える
ご隠居:
「それではこういう話がある。唐土(もろこし)の有名な学者と麹町のさる殿様の話だ」

お崎:
「モロコシの役者に猿の殿様ですか?」
よくわかっていないお崎だがご隠居は続ける
ご隠居:
「孔子の留守中に厩(うまや)が火事になり、大事にしていた馬が死んでしまった。使用人たちは大変なことになったと恐縮したが、孔子は咎めることなく使用人たちの無事を喜んだ
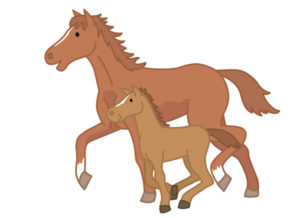
一方、麹町の殿様は家宝の皿と一緒に階段から落ちた女房を見て"皿は無事か"と言ったそうな。結局離縁になり、その悪評が世間に広まって家は没落したという
そこでおまえも八五郎の大事にしている瀬戸物を目の前で割って見せて、やつが孔子なのか殿様なのか試してみてはどうだろう」
早速お崎は家に帰ると八五郎の大事にしている瀬戸物を転んだ振りをして割ってしまう。

八五郎:
「お崎!怪我はないか!」
飛んできてお崎の身体を気遣う八五郎
お崎:
「うれしいよ、そんなにあたしの体が大事かい」
八五郎:
「当たり前だ。おまえが怪我をしたら明日から遊んでいて酒が飲めねえ」
落語 厩火事女性の髪結いについて
落語 厩火事について。
八五郎の最後のセリフは本心なのか照れ隠しなのか知る術がないのは残念です^_^;
町人の男性はわりと頻繁に髪結い床(いわゆる床屋)に通っていました。月代(さかやき)は自分では剃れないためです。
女性は自分で髪が結えて一人前という意識があり、基本的には自分で髪を結いましたが、裕福な商家の女性などは女性の髪結い師に結わせていました。
髪結い師の女性を芝居や花見などに一緒に同席させ、出先でも髪を直させたそうです。
裕福な女性の専属の髪結いとなると給金もかなりよく、髪結いの亭主という言葉もあり、半ばそれが職業のような男性もいたとか
噺の中の八五郎はどう考えてもゴクツブシのようですが…
ちなみに長屋の女房は専業主婦が多く収入があったとしても内職くらいでしたので、手に職がある女性の髪結い師は貴重な存在でした。
その他の中国の故事が出てくる噺
-

-
落語 二十四孝(にじゅうしこう)のあらすじ 中国の書物二十四孝とは?
落語 二十四孝(にじゅうしこう) 乱暴者の熊五郎が大家さんのところへ駆け込んでくる 何でも母親と些細なことで喧嘩をし、母親に味方したおかみさんまで追い出したいから離縁状を二通書いてほしいという あきれ ...
続きを見る