落語 小間物屋政談
働き者で評判の小間物屋 相生屋小四郎。
江戸から上方へ行商に行くことを伝えるため大家さんの元を訪ねた
小四郎は自分が留守の間、女房のおときのことが気がかりな様子
大家:
「安心しなさい。私がちょくちょく顔を出して変な虫がつかないか見張っておくよ」
大家さんにおときのことを頼んで安心して旅に出る小四郎だが
小田原を出たところで事件に出くわしてしまう。林の中で縛られている人を発見したのだ。

その人の縄を説いてやるとなんと同業者 神谷町の大店の店主 若狭屋甚兵衛だという。気の毒に思った小四郎は甚兵衛に自分の普段着の茶弁慶の着物と路銀を貸してやる
甚兵衛:
「ありがとうございます。あなたはこれから上方ですか。私は江戸に戻ったらお借りしたお金を留守宅に返しに参りますから、住まいを教えてください」
そこで小四郎は「京橋源兵衛店相生屋小四郎」と書付を渡すと、甚兵衛はそれを服の袂にしまい「お互いご無事で」と、その場は分かれた。
甚兵衛は江戸への帰り道、小田原へ着くと宿に入るが、たまたま客が重なったのと身なりがよくなかったため、宿帳も取らずに粗末な部屋に通されてしまった。
その晩甚兵衛は山中での寒さが堪えたのと元々身体が弱かったこともあり、体調を崩してしまう。
女中が看病をするが、ない寿命とみえて夜中に息を引き取ってしまった。
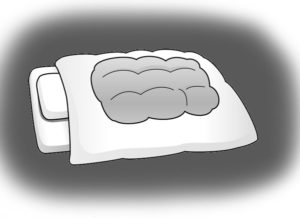
亡くなってしまった上に、宿帳を取ってないのでどこの誰だかわからない。仕方がないので宿の者が甚兵衛の着物を探ってみると「京橋源兵衛店相生屋小四郎」という書付が出てくる。
「ああこれがこの人の名前と住まいだ」と宿の主人は使いのものを走らせる
小四郎が死んだという知らせを聞いてワッと泣き出す女房のおとき
遺体を検めに行かないといけないがどうもそんな状態ではない
大家さんが代わりに本当に小四郎なのか検めに行くことになる。
宿のついた大家さんだったが、なんせ日が経っているので何だか嫌な匂いがする。いくら大家と言えば親も同然といっても、そんな遺体にあまり近づきたくない。
遠くから見ると小四郎と背格好が似ているのと普段着にしている茶弁慶の着物を着ていたので「これは小四郎に間違いない」と判断。仏さんを火葬して長屋に戻り弔いをすませた。
一月ほど経ったある日「まだ早い」というおときに強引に縁談をすすめる大家さん
大家:
「こういうのは早い方がいい。ボヤボヤしてると変な男が寄ってくるから。おまえが幸せになるのが小四郎への一番の供養だし、いい相手がいるんだ」
と話を聞いているうちに説き伏せられてしまう。
相手は小四郎の従兄弟の三五郎で最初は抵抗のあったおときだったが三五郎の優しいこと。すっかり仲のいい夫婦が出来上がってしまった。
そしてある晩のこと

小四郎:
「おとき開けとくれ、おとき」
死んだと思っていた小四郎が帰ってきてしまい関係者は大慌て
小四郎から小田原で茶弁慶の着物と書付を若狭屋甚兵衛に渡したことを聞くうちに大家さんは勘違いに気付く
大家さんはおときに事情を説明して小四郎と元の夫婦に戻そうとするが、おときは三五郎の方を選んでしまう。女房も家も失った小四郎に
大家:
「小四郎 なったもんは仕方ないあきらめろ」
大家さんに留守中のことは頼んでいったのに、納得のいかない小四郎は奉行所に訴え出る
お白洲に並ぶ小四郎たち。裁くのは名奉行大岡越前守だが
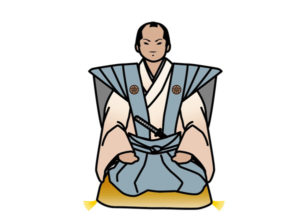
その名奉行にも小四郎は
大岡:
「そちはもう一度旅に出よ。旅はいいぞ」
と言われ自暴自棄になって悪態をつく。
次に聞き取りが行われたのは、若狭屋甚兵衛の未亡人であるヨシ
大岡はヨシに若狭屋の使用人は何人いる?甚兵衛との間に子はおるか?と聞いていくと、小四郎は若狭屋のとんでもない金額の財産に目をパチパチするばかり

そして最後に
大岡:
「甚兵衛に情けを掛けた小四郎が今このように路頭に迷っておる。ヨシ そちは小四郎と夫婦になるつもりはないか?」
ヨシ:
「はい。小四郎様も私と同じ小間物屋。これも仏のお導きと思います」
小四郎が隣に座るヨシの姿を見るとその美しいこと おときとは比べ物にならない
もうおときのことはどうでもよくなった小四郎は
小四郎:
「はい私が今日から若狭屋甚兵衛になります。大岡様ありがとうございます、ありがとうございます」
さっきまで悪態をついていたのにそれはどこへやら
小四郎:
「大岡様はやはり名奉行だ。この小四郎 このご恩は生涯しょいきれません」
大岡:
「小四郎そなたは今日から若狭屋甚兵衛じゃ。しょう(背負う)には及ばん」
落語 小間物屋政談小四郎の職業小間物屋とは

落語 小間物屋政談について。
文字にしないとわかりにくいサゲですが、おまえは大店の店主になるんだから背負い(しょい)で行商に出る必要はないぞという意味になります。
背負いとは背負子(しょいこ)のこと。二宮金次郎が背中で薪を運んでいるあれを想像してもらえればいいかと思います。
今でもアウトドアでは両手が塞がらないので重宝されているようで、楽天市場なんかでも扱っているようです(笑)
小間物屋とは女性用に櫛、笄(こうがい)、化粧品を扱った業者
店頭で販売する大手業者と、個人で行商で売り歩く背負い(しょい)に分けられました。小四郎は後者のタイプで江戸の商品を上方(大阪京都)に持っていき、現地で商品を仕入れてまた江戸に持ってくる販売スタイルだったと思われます。
女性用の商品を扱うだけあって、色男が多かったといわれています。
この辺りは現代にも通じる部分ではないでしょうか。
その他政談もの
-
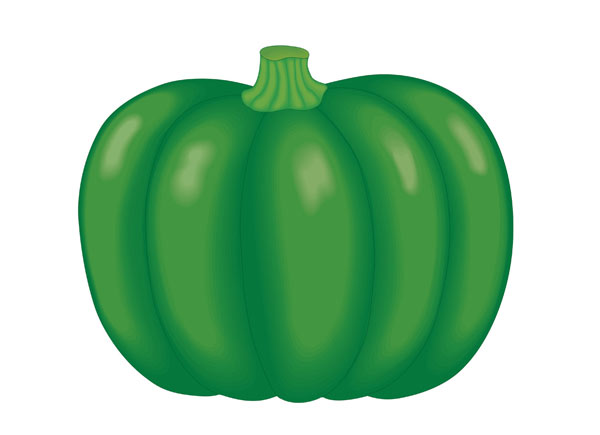
-
落語 唐茄子屋政談のあらすじ 江戸時代の勘当とは
落語 唐茄子屋政談 道楽三昧の挙句、とうとう大旦那から勘当を言い渡された若旦那。 家を出た若旦那は最初は太鼓持ちや吉原の馴染みの女郎のもとを渡り歩くが金の切れ目が縁の切れ目か、結局は体よく追い払われて ...
続きを見る