落語 黄金餅
ケチ坊主の西念が病で寝込んでいると聞いて隣に住む金兵衛が見舞いに来る
「医者に見てもらったか?薬は飲んだか?」とたずねるが、西念は
「金がかかるからそんなものはいらない」という

「じゃあ何か食べたいものは?」と金兵衛が聞くと
西念:
「あんころ餅が食べたいが金がもったいない。金兵衛さんが言いだしっぺなんだから買ってきてください」
まったくしょうがない奴だなと言いながらも買ってきてやる金兵衛
しかも人が見ている前では食えないと勝手放題の西念
どうにも西念の行動が気になる金兵衛は隣の自分の部屋に帰ると錐(きり)で壁に穴を開けてそこから様子を窺った。
見られているとは気付いていない西念は先程のあんころ餅から餡子を取り除くと、胴巻きから金を取り出して餅にくるんで飲み込み始めた。
金兵衛:
「西念のやつ 貯め込んだ金をあの世に持ってくつもりか?」
すべての金を飲み込んだ西念だったが、そのうち苦しみ始める。
慌てて金兵衛は駆けつけたが西念は息絶えてしまう。
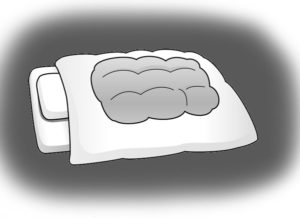
なんとか金を手に入れたい金兵衛は大家さんの元へ
金兵衛:
「隣の西念さんが亡くなりまして、葬式のことは私に一切任せると言い残されました」
すぐに棺桶を手配すると みんな忙しいから今日中に弔いを済ませようと長屋の連中に棺桶を担がせて菩提寺のある麻布絶口釜無村の木蓮寺へ
酔っ払った坊主にお経をあげてもらい弔いが済むと長屋の連中を帰らせて金兵衛一人で焼き場へ向かう

金兵衛:
「お~いこの仏を焼いてくれ ただし遺言で腹だけは生焼けにしてくれ」
火葬場の者に無茶なお願いをして自分は近くの飲み屋へ
そして明け方戻ってくると、用意していた包丁をグサりと西念の腹に突き立てる
金兵衛:
「あったあったこれだ!」
腹からは金がザクザク
金兵衛はこの金を元手にして餅屋を出しました。たいそう繁盛したと言うことです。
これが黄金餅由来の噺
落語 黄金餅西念が飲み込んだ金とは?

落語 黄金餅について
貯めこんでいた金というと小判を連想してしまいますが、天保8年より鋳造された天保小判のサイズが縦5.9cm×横3.2cmほど
餅に包んで飲み込むには厳しいサイズと考えられます。
同じ金でも飲み込むなら一分金あたり サイズは時期によって異なりますが2.3cm×1.4cmほど
(一朱金というもっと小さいものもありましたが、金の純度が低く金としての価値も低い)
これなら頑張れば飲み込めそうです^_^;
余談ですが江戸時代一分金と一分銀というものが存在しており同等の価値がありました。
これが外国人に目をつけられて日本国内から外国へ金が流出する原因になってしまうのですがそれはまたの機会に