落語 お菊の皿(皿屋敷)
町内のヒマな若い衆がご隠居の元をたずねる。目的は「今度皆で肝試しをしたいが どこかに怖いものはないか?」というもの。
肝試しということならうってつけの場所があるとご隠居は少し離れたところにある皿屋敷のことを教える。

ご隠居:
「その屋敷にはお菊という奉公人がいたのだが、主人の大切にしていた十枚組の皿の一枚を割ってしまう
主人は激高してお菊を手討ちにし、遺体を井戸に投げ込んだ。
ほどなく井戸の底から成仏できないお菊の皿を数える声が聞こえるようになる…」

若い衆:
「そりゃあいい 今日にでもみんなで行ってきます」
ご隠居:
「皿を最後まで数えるところを聞いてしまうと祟りで死んでしまうそうだ。途中で逃げるんだぞ」
若い衆たちはその晩のうちに件の皿屋敷へ。なるほどご隠居のいうとおり古ぼけた井戸がある。

お菊の幽霊は今のところ出る気配はない。「六枚目あたりで逃げりゃいいやな」と馬鹿話をしている間に時刻は草木も眠る丑三つ時
どこからともなく生暖かい風が吹いてくる そして女のすすり泣く声に続いて
お菊の幽霊:
「いちまぁい、にまぁい…」

若い衆:
「ギャーほんとにでたー!」
逃げ出す若い衆 この噂が広まって 本物の幽霊が見られるなら一目見ようと見物客達が井戸に集まってくる
押すな押すなの人だかりの中に酒や饅頭を売る出店まで出るものだから辺りはギュウギュウ詰め
見物人:
「これじゃあ身動きが取れないな お?時間か?」
生暖かい風に続いて女のすすり泣く声 お菊が現れた

お菊:
「いちまぁい、にまぁい…ろくまぁい…」
見物人:
「六枚目だ!それみんな逃げろ!」
そう思ったが逃げる者、腰を抜かす者、酒を飲んで寝転んでいる者 人が多過ぎて大混乱!前に進めない
お菊:
「ななまぁい、はちまぁい…」
見物人:
「ああ!もうだめだ!」
と思っていたら
お菊:
「じゅうろくまぁい、じゅうしちまぁい、じゅうはちまぁい」
結局お菊は18枚まで数えてしまった
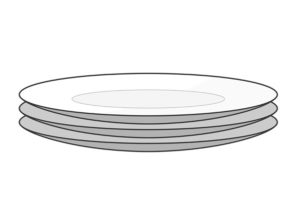
見物人:
「お菊さん なんで18枚まで数えたんだい?」
お菊:
「二日分数えて明日は休ませてもらいます」
落語 お菊の皿(皿屋敷)全国いたるところにあるお菊の井戸と皿屋敷
落語 お菊の皿(皿屋敷)について
恨みを持って死んだ人間がそれを晴らすために怨霊となって現れる定番の怪談のためか、四谷怪談のお岩さんと混同されがちな皿屋敷のお菊さん。
怪談話や肝試しは江戸っ子の大好物だったらしく、さまざまな百物語や妖怪関連の本が本気で出版されていたりもしました。
お菊の話も皿屋敷の元ネタとされる物語(歌舞伎、浄瑠璃)は複数あり、お菊さんが投げ入れられたと伝わる井戸にいたっては全国で50箇所近くあるそうです。(お菊さんが葬られたと言われるお墓も多数)
現代に比べて娯楽の少なかった江戸時代。噺の中のような肝試しのため、または夏の納涼のために全国に皿屋敷の物語が用いられたのではないでしょうか。
その他女性の幽霊が出てくる噺
-

-
落語 三年目のあらすじ 死者の髪の毛を剃る意味とは?
落語 三年目 病気の妻をやさしい夫が一生懸命に看病するが、一向によくならない。 自分の死が近づいているのを悟ったか、妻は心残りになることがあると夫に打ち明ける 妻: 「あなたはまだお若いから 私が死ん ...
続きを見る