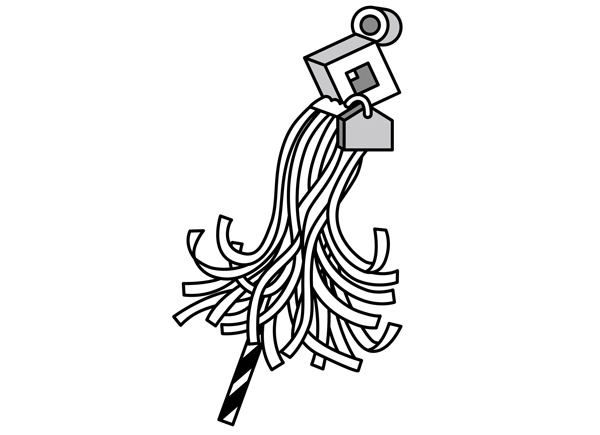落語 ねずみ穴
親の遺産をすっかり食いつぶしてしまった遊び人の竹次郎が借金を申し込みに兄の元をおとずれる。
兄は竹次郎とは逆に親の遺産を元手に商売をはじめ、今では表通りに大店をかまえるほどの資産家だ。

借金なんて格好悪いが背に腹は代えられない。世間話の後にお金の話を切り出した。
すると兄はそれならばと お金を渡してくれたがよく見るとたったの三文(現代の価値で約75円)
冗談だと思っていた竹次郎だったが、兄はどうやら大真面目な様子

竹次郎:
「こんなの子供の駄賃だ バカにしやがって」
兄:
「飲んだ帰りに寄りやがって、今いくら貸したって酒代に消えちまうだろう。だったら三文でじゅうぶんだ」
口論になったが結局追い返されてしまった。これで負けん気に火が付いた竹次郎はきっぱりと酒をやめ昼夜を問わず働いた。
その頑張りが功を奏し、所帯を持てるくらいに生活を再建し、10年経つ頃には兄にも負けないくらいの店と土蔵まで建てるまでになった。

竹次郎は あの日借りた三文に利息二両を合わせて兄に叩き返してやろうと考える。
竹次郎:
「留守にするから土蔵のねずみ穴に目塗りをしておくんだぞ。しっかり火の用心も頼むぞ」
火の用心を番頭に言いつけて兄のところへ向かう竹次郎
10年ぶりの兄との再会。竹次郎は10年前に借りた三文の話を兄に切り出す。
竹次郎:
「これはあの時の三文だ!どんな苦しい時でもこの三文を見てぐっと堪えて頑張ったんだ!今ここで利子をつけて返してやらあ」
しかし兄は穏やかな声で
兄:
「あの時 お金を貸そうとは思ったのだが、このままではいけない。おまえに生まれ変わってほしくて心を鬼にして三文を貸した。よくぞここまで頑張ったなあ…」

と兄の真意を聞いて恥じ入る竹次郎。久しぶりの再会ということで兄弟二人で酒を酌み交わし、気がつくともう夜中。土蔵のことが気になるから帰るという竹次郎だったが、兄が引き止める。
兄:
「万一おまえの土蔵が燃えたなら、俺の財産を全部やろう。だから今日は泊まっていけ」
そこまで言うならと泊まることになった竹次郎だったが、心配というものは当たるもので、店のある方向で大火事がおこる。

竹次郎:
「あれほどねずみの穴に目塗りをしておけと言ったのに…」
店も土蔵も全焼して全財産を失ってしまった竹次郎。
仕方がないので、娘の手を引いて兄のところへ借金を申し込みに行くが、全財産をやると言ったくせに「あれは俺ではなく酒が言ったことだ金は貸せない」という。
やっぱりヒドイ兄だ。途方に暮れて歩いていると、娘がこんなことを言う
娘:
「私が女郎になれば お金が借りられるでしょう。だから今から女郎屋に行きましょう」

なんとも情けない話だが、火事ですべてを失った竹次郎にはそれしか再起する方法がない
女郎屋に行き 娘と引き換えに五十両を借りるが 帰り道にスリにやられてまた一文無しに…
もうどうしようもなくなって木に縄をつけて首を吊ろうとしていると…
兄:
「おい!どうした?悪い夢でも見ているのか」
竹次郎がうなされているのに驚いた兄に揺り起こされる。まわりを見ると兄の家で先ほどの光景は夢だったようだ。
竹次郎:
「なんだ夢だったのか…蔵のことを気にしすぎたな。
夢は土蔵(五臓)の疲れだ」
落語 ねずみ穴わかりにくいオチ 五臓の疲れとは?
落語 ねずみ穴について
現代では心労やストレスが重なると眠りが浅くなり 悪夢を見やすくなるといわれています。
しかし江戸時代、五臓(内臓)が疲れると悪い夢を見ると考えられていました。ではなぜ内臓が関係あるのか?
私達現代人が物事を考えるとき頭(脳)を使うというのは常識です。しかしその常識も意外と歴史が浅く 西洋医学の広まる明治期まで物事は 心臓をはじめとする臓器で考えていると解釈されていました。
つまり 心がお腹の中にあると考えられていたということです。
その名残が
心臓(心のある臓器)
腹を割って話す(本音を正直に言う)
腹黒い(悪いことを考えている)
自分の胸に聞いてみな といった言葉に残っています。
現代の常識では内蔵で考えるなんて想像もつきません 江戸時代の人にとっての頭の役割って一体…(笑)
その他ちょっとわかりにくいオチで火事が出てくる噺