落語 そば清
そばなら何杯でも食べることができると豪語する旅商人の清兵衛
その見事なそばの食べっぷりからついたあだ名は「そば清」
本業の傍ら、そばの大食いで賭けをして小銭を稼ぐのが日課となっている。
今日はそば30枚を平らげたら一分をやるという長屋の男達に挑まれるが
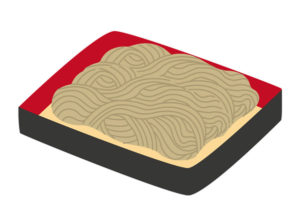
清兵衛:
「それにしても、ズルズル…なかなか…ズルズル…30枚も食べるなんてことは…ズルズル…大丈夫ですかねえ…あれ?今何枚目ですか?」
男:
「なんてこった30枚食っちまったよ」
あっさりと一分をとられてしまった男達は引き下がれない、今度はそば50枚食えたら一両やると勝負を挑む
そばを食うだけで一両もらえるというのなら大層な額だが、さすがに食べきれるかどうか微妙なところだ
だが勝負を受けられないと言えばそば清の名が廃る
清兵衛は「今日のところは仕事がありますのでまた後日」とその場は言い繕って商売に出かけた
さて清兵衛が仕入れを終えて 信州からの帰りの山道を歩いているとうわばみ(大蛇)が人を丸呑みするのを目撃してしまう
さすがのうわばみも人を丸呑みして腹が苦しい様子
だが、近くに生えている黄色い草を一口食べると、みるみる大きなお腹が引っ込み涼しい顔をしてどこかへ這っていってしまった
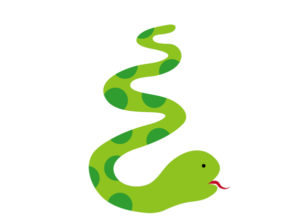
「しめしめ これは食べたものを消化する草だ」と思った清兵衛は、その草を摘んで江戸に帰る。清兵衛はそば屋に現れると
清兵衛:
「この間の勝負 今ここで受けましょう」
と宣言するとうずたかく積まれた蒸篭(せいろ)がズラリと並べられ 大勢の野次馬も集まってくる
勝負が始まり20枚、30枚とそばが清兵衛の腹の中に消えていくが、40枚 この辺りからさすがに苦しくなってくる
ここが勝負所と思った清兵衛は、休憩を申し出ると厠へ駆け込んだ。そこで用意しておいた例の黄色い草をパクり
一方男たちは清兵衛がなかなか戻ってこないので「さては逃げたな」と厠の扉を開けると
清兵衛の姿はなく、そばが羽織を着て座っていた
※一両=10万円ほど 一分はその四分の一で2万5千円ほど
落語 そば清オチのそばが羽織を着て座っていた理由
落語 そば清のオチについて
清兵衛が持ち帰った黄色い草は食べたものを消化する草ではなく実は人間を溶かす草だったため、食べた清兵衛は溶けてしまい羽織と直前に食べたそばがその場に残されたという意味
蛇足でしたでしょうか^_^;
「そばの羽織」という題名で演じられることもあります。
落語 そば清余談記録に残されているそばの大食い記録
江戸時代にも大食いイベントというのは催されていて、信じられないような記録も残されています。
そばの部だけを見てみると優勝者が中盛を63杯、準優勝が57杯という記録が残っています。50枚平らげる人はいたのかもしれません。この記録が本当であればの話ですが…
ただ江戸時代は19世紀の飢饉の時期を除けば食料の供給が豊かで平和な時代であったことがうかがえます。