落語 二番煎じ
寒い夜の番小屋に町の旦那衆が夜回りのために集まっている。
夜回りのために外に出てみたものの寒くて仕方がない
ブルブル震えながら
「火の用心~」

寒くて声は消え入りそうだし、拍子木を懐に入れたまま叩くというありさま。まったく音が聞こえやしない。
他の者も似たようなもので寒い寒いと肩をすぼめて歩いているだけで、まったく夜回りの意味がない。
やっと町内を一回りしてきて番小屋に戻ってくると皆が一斉に火の回りに集まった。

すると旦那の一人が懐から瓢箪をこっそりと取り出す。家の者が風邪をひかないように持たせたのだという。
「酒はいけないよ」
と別の旦那がいうが内心はそうは思っていない。他の者もちゃっかり酒や鍋の具材を持ってきており、中には土鍋を背負ってきた強者も。
それを合わせていつのまにか酒盛りの準備ができあがる。番小屋での飲酒はご法度だが、煎じ薬ということにしてしまおうということで話はまとまってしまう。
役人の見回りに見つかると大変だが 戸に心張棒を立ててどんちゃん騒ぎが始まった。
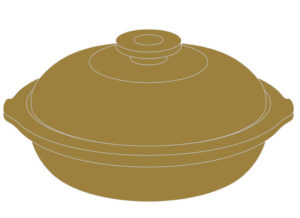
ドンドンドン
役人:
「戸を開けぬか」
そこへタイミング悪く役人が見回りにきてしまい、急いで隠したが土瓶に入れた酒を見られてしまう。
役人:
「これはなんだ?」
と聞かれとっさに
旦那:
「風邪を引いたので煎じ薬でございます」
役人:
「ちょうどよい私も風邪を引いておるので一杯もらおう」
飲まれたらウソがバレてしまうとドキドキしながら湯飲みを差し出す

役人は一口飲んでニヤりとする
役人:
「ほほう これはいい煎じ薬だ」
結局咎められなかったが、酒はすべて飲まれ、鍋もあらかた食べられてしまう
役人:
「煎じ薬はもうないのか?」
旦那:
「もうありません」
それを聞いた役人が
役人:
「ならば私は一回りしてくるから二番を煎じておくように」
※二番煎じ:一度煎じた薬草に水を足して煮出した薄くなった薬のこと。お茶の出がらしをさす場合も
落語 二番煎じ 治安維持のために設置された番小屋
落語 二番煎じについて。
江戸時、代庶民たちによる町内の治安を守るシステムがありました。
各町内に配置された警備のために、木戸番と自身番という詰め所があり、噺に登場するのは自身番のほうです。
最初は地主自身が交代で番所に詰めていたことから自身番と呼ばれるようになり、時代が下ってくると大家(長屋の管理人)や町で雇った番人が詰めるようになりました。
見回りのほか不審者を捕らえて留めておき、奉行所に差し出したり、取調べのようなことも行われ交番兼留置所のような役割も果たしました。

また自身番の詰め所の多くは火の見櫓が併設されていて、火事を発見したら半鐘を打ち鳴らす役割があり、噺の中ではのんきに見えますが責任は重大で、飲酒がご法度というのもうなずける話です。