落語 三年目
病気の妻をやさしい夫が一生懸命に看病するが、一向によくならない。
自分の死が近づいているのを悟ったか、妻は心残りになることがあると夫に打ち明ける
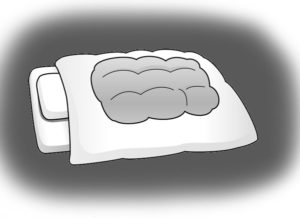
妻:
「あなたはまだお若いから 私が死んだら新しい奥さんをもらってその人を可愛がる。それを想像すると気になって…」
夫:
「馬鹿なこと言っちゃいけない。私は新しい奥さんなんてもらうつもりはないし、もしもの時は婚礼の夜に幽霊になって出てきなさい。そうすれば悪い噂が立って縁談なんて来なくなるだろう」
妻:
「では八つの鐘を合図に枕元に立つことにします…」
変な約束をしたものだが、妻は自分が死んだ後、夫が再婚に乗り気じゃないのを確認すると安心したのか、まもなく看病の甲斐なく亡くなってしまう。

約束はしたものの四十九日、百箇日と過ぎて行くと周りが放っておかない。「おまえさんはまだ若いんだから」と縁談がくるようになる。
夫はだんだん断りきれなくなって、結局は新しい奥さんと再婚することになってしまった。

祝言も滞りなく終わり、迎えた婚礼初日の夜 夫は前妻との約束が気になって眠れない。新妻には「今日は早く寝なさいと」言って、前妻が現れるのを待っていたが八つの鐘が鳴り終わっても現れる気配がない。
夫:
「遠く十万億度の彼方から来るんだ さすがに初日は無理か」
と二日経ち三日経ち…いっこうに前妻の幽霊が現れないので段々起きているのも面倒になってきた
すると元々 新妻とも仲が悪いわけでもなく夫婦仲は円満だし、そのうち子供も授かった
時は流れて前妻が亡くなってから三年が過ぎた。法要を済ませた晩、夫は夜中に胸騒ぎがして目が覚めた。生温かい風が吹いて、障子にサワサワと何かが触れる音がする。
「何かおかしいぞ」と思っていると前妻の幽霊が枕元にうらめしそうに座っている。
前妻の幽霊:
「あなた…約束が違います…」
夫はびっくりしたが、幽霊に掛け合った
夫:
「約束が違うのはこっちも同じだ ずっと待ってたのに子供も出来た今頃出てくるなんて」
前妻の幽霊:
「無理よ…あなたは私を棺に収める時、髪を剃ってお坊さんにしたでしょ…」
夫:
「ああ したよ。親戚中一剃刀ずつ当てて棺に収めたよ」
前妻の幽霊:
「坊主頭だとあなたに嫌われると思って…髪が伸びるのを待ってました…」
※時刻の八つ=現代の午前2時頃
落語 三年目オチの意味と死者の髪を剃る風習について
落語 三年目について
今ではほとんどない風習ですが、江戸時代の葬儀では、髪剃(こうぞり)といって死者の髪を剃って戒を授けてから埋葬しました。
早い話が死者をお坊さんにしてあの世に送り出したということで、その時付けられるのが戒名と言うわけです。
「お坊さんになる=仏弟子になる」 すなわち成仏して、この世に未練を残して帰ってくるなという考え方です。
オチの意味ですが、奥さんを棺桶におさめる時 お坊さん(尼僧)風の坊主頭にしてしまいました。坊主頭では恥ずかしくてあなたの前に出てこれず、髪が伸びて姿をあらわせるまで三年かかりました。という意味になります。
気になるのが亡くなって一年目が一周忌法要、二年目が三回忌、三年目はとくに年忌には当たってないところ。
祥月命日に法要を営んだのでしょうか^^;
他にも女性の幽霊が出てくる噺。幽霊として出てくるのはなぜか女性の方が圧倒的に多い?
-

-
落語 野ざらしのあらすじ オチの馬の骨だったか!の意味とは?
落語 野ざらし 長屋の八五郎が隣に住む先生の元をたずねる。 昨晩先生と一緒にいた女は誰なのか?話し声が気になって眠れなかったと文句を言いに来たのだ。 あれを見られてしまったのだったら仕方がないと先生は ...