落語 もう半分
夫婦で営む居酒屋に湯飲みに酒を半分ずつ注文する老人が毎日やってくる。
ある日、いつものように飲み始めた老人だったが「もう半分だけ、もう半分だけ」といつも以上に杯を重ね、痛飲しているように見える。
飲み終わってよろよろと店を出た後、席に風呂敷包みが残されているのに主人が気付く
主人:
「大変だ今から追いかければすぐ追いつけるだろう」
女房:
「いいよほっときなよ。それより大事そうに風呂敷だよ 何が入ってるか見てみなよ」
女房が風呂敷包みを解くと、なんと中から出てきたのが五十両という大金。これは大変だと慌てる主人を横目に黙っておきなと制す女房

しばらくすると血相を変えて老人が戻ってくる
老人:
「ここに風呂敷包みはありませんでしたか?」
女房:
「ここには何もありませんでしたよ」
老人:
「あれは娘が吉原に身を売って作ってくれた金なんです。返してくれませんか」
女房:
「なんて人聞きの悪い…泥棒扱いするなんて!もう看板なんですから帰ってください」
お金を失い落胆した老人は永代橋から身を投げて死んでしまった。

一方夫婦の店は老人から奪った金を元手に店を大きくして商売も順調そのもの。さらに子宝にも恵まれる。
待ち焦がれた赤ん坊の誕生だったが、どうも様子がおかしい。生まれてきた赤ん坊は、髪が真っ白、顔には深い皺が刻まれており、あの時の老人そっくりなのだ。
あまりのことに驚いた女房は寝込んでしまい間もなく死んでしまった。
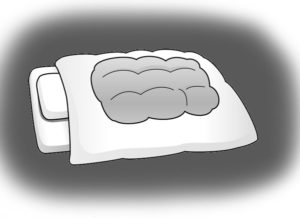
残された主人は乳母を雇って赤ん坊の面倒を見させるが、誰もが一晩でヒマがほしいと辞めていってしまう。
不思議に思った主人が子供を一晩中見張っていると、深夜に這い出してきた赤ん坊が油さしから油を茶碗にそそいて飲み始めたではないか。
主人:
「おのれ化物め」
すると赤ん坊が茶碗を差し出して
赤ん坊:
「もう半分だけ…」