落語 居残り佐平治
遊び人の佐平次が仲間に品川の遊郭に繰り出して派手にやろうと提案する。
佐平次:
「お前たちの割り前は俺が預かるから後の分は俺に任せろ」
その晩は芸者も総揚げし幇間も呼んでのどんちゃん騒ぎ
翌朝、「お金は母親に届けてくれ、しばらく俺はここで養生するから」と頼んで仲間を見送ると自分は居残って朝からまた飲み始める。
当時の品川は海が近く魚はうまいし酒もすすむ。朝風呂に入り出るとまた酒を注文したり…

とそこで店の若い者が「一度お勘定を…」と催促するが
佐平次:
「夜になれば昨夜の連中がまたやってくる、また昨日の続きだってことで陽気に飲んで、帰りは俺も一緒。勘定はその時だ。商売人ならもう少し気をまわしてほしいもんだな」
うまいことはぐらかされてしまう。
その夜、佐平次は一人で飲み始めたが昨日の一行はやってこない。店の者がおかしいと思い佐平次を取り囲むとなんと一文無しだと開き直る。
腹は立つが、ないやつから金を取りようがない。ただ一文無しに座敷を占領されてちゃあ商売にならないということで、佐平次は布団部屋に軟禁されてしまう。
その晩店は若い衆もてんてこ舞いの大忙し、どう考えても人手が足りてないようで勝五郎という常連客を待たせてしまっている。
遊女はこないわ、刺身につける醤油はないわで、そろそろ我慢も限界というところで、ひょっこりと醤油を持って現れる佐平次

佐平治は勝五郎を上手くおだてて酒やご祝儀までもらってしまった。後から部屋に来た遊女に「この男は店の者ではなく居残りの男だ」と明かされても勝五郎は悪い感じはしない。
機転はきくし幇間のように酒の相手ができて話も達者。いつの間にか馴染みの客が出来て "居のどん、居のどん"と座敷に指名が入るようになる。

そうなると面白くないのは店で働く若い衆。居残りに仕事を取られていると主人に掛けあった。これには主人もいつまでも居残りを放っておくわけにいかなくなる。
若い衆:
「おい、居残りさん」
佐平次:
「へい、今度はどちらのお座敷で?」
若い衆:
「御座敷じゃない。主人があんたに話があるそうだ」
店の者から苦情を受けている主人は佐平次に、「勘定は後でもいいから帰ってくれないか」と頼み込むが、ここで佐平次はとんでもないことを白状する。
佐平次:
「実は私はお尋ね者でして、ここから出るとあっという間にお縄を頂戴してしまいます。もうしばらく匿ってはもらえませんか?」

そんなことを聞く前ならいざ知らず、聞いてしまってはいつまでもここに置いておくわけにはいかない。お金はいいから早く出て行ってくれと頼むが、先立つものがないという。
結局、逃亡用の路銀だけでなく、着物、帯、紙入れなども佐平次にうまいことせしめられてしまう主人。佐平次は悠々と店を出て行く。
すぐに佐平次が捕まるのではないかと気になった主人は店の若い衆に後をつけさせるが、お尋ね者にしてはどうものんびりしていて様子がおかしい。不審に思って声を掛けてみると。
若い衆:
「おい、居残りさんよ やけに上機嫌じゃねえか。逃げる気はあるのかい?」
佐平次:
「おう、おまえも遊郭で飯を食っていくんなら俺のことは覚えときな。俺は居残りを生業にしている人呼んで居残り佐平次っていうんだ」
だまされたことに気が付いた若い衆は店に戻ると主人に顛末を報告する
主人:
「なんてやつだ。どこまで人のことをおこわにかけるんだ」
若い衆:
「それは旦那の頭がゴマ塩ですから…」
落語 居残り佐平治オチのおこわにかけるとゴマ塩について
落語 居残り佐平治について。
遊郭で御馴染みの吉原の通称が北なら 品川は南と呼ばれていました。品川宿は表向きは遊郭ではなく個々の宿屋に表向きは宿の従業員という体裁で働き、夜には客の相手をする飯盛り女という女郎がいました。
サゲの「おこわにかける」とは「一杯食わされた」「騙された」という意味になります。主人の頭髪がゴマ塩頭(髪に白髪が混じっていた)のとかけたもの。現代では解説がないとまったくわからないため、こういうパターンもあります。
路銀や着物をせしめて堂々と表から帰って行く佐平次の後姿を見て
若い衆:
「旦那 どうして裏から返さないんです?」
主人:
「裏を返されたらたまらない」
裏を返す=遊郭でリピーターになるという意味で「あんな奴にもう一度来られたらたまらないよ」という考えさせるオチ
裏を返すという用語も落語ファンには御馴染みかもしれませんが、こちらもちょっと通じにくいかもしれませんね^_^;
他の遊郭が出てくる噺
-
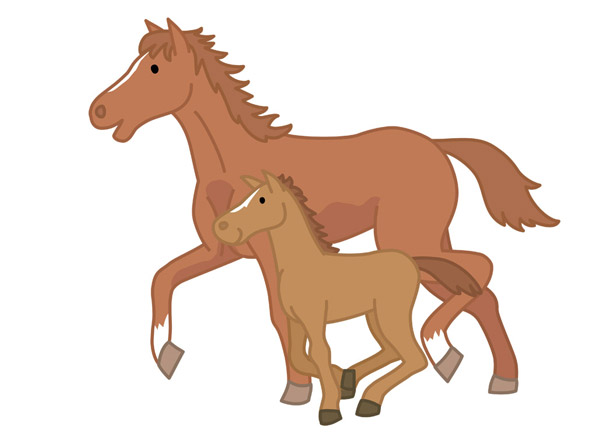
-
落語 付き馬のあらすじ オチの馬に行けとは?遊郭での勘定のルール
落語 付き馬 吉原のある店に金持ち風の男がと登楼してくる。その晩 男は芸者や幇間入り乱れてのドンちゃん騒ぎ 翌朝 店の若い衆が勘定書を持って行くと男は「昨晩は久しぶりに楽しかった これからも贔屓にして ...
続きを見る