落語 三枚起請
吉原の花魁にいれこんでいる猪之(いの) それを棟梁が「本気になるなと」釘を刺すが、猪之は「俺だけじゃなく相手も本気だ」と言い張る
その証拠に年期があけたら夫婦になるという誓いの言葉を書いた起請を貰っていると得意顔

棟梁がそれを見せてもらうと 「自分も同じものを持っている」と言い出す。なんてことはない二人とも起請の発行主である喜瀬川に騙されていたのだ
そこへ長屋の金公がやって来る。
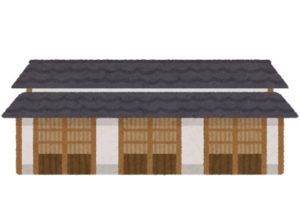
二人が喜瀬川に騙されたことを聞くと
金公:
「女郎なんて騙すのが仕事なんだ こんなので喜ぶなんて二人とも長生きするよ」
しかし二人の持っている起請を見てびっくり 金公も同じものを持っており 三人揃って喜瀬川に騙されたことに気付く
三人は復讐しようとお茶屋へ行き猪之と金公は屏風の裏と戸棚に隠れて棟梁が喜瀬川を呼び出した

愛想を振り撒く喜瀬川だったが棟梁が起請のことを問いただす
棟梁:
「猪之にも同じものをやっただろう」
喜瀬川:
「猪之みたいな色白のブクブクに書くわけないよ」
猪之の悪口を散々言っているところへ隠れていた猪之が登場
猪之:
「この女狐め!金公にも書いただろう」
喜瀬川:
「金公みたいな無粋な男に…」
今度は金公の悪口を言い出したところへ金公本人が登場 さあ侘びでも入れるかと思ったら喜瀬川は開き直るばかり
棟梁:
「嘘の起請を書くと熊野でからすが三羽死ぬっていうぜ 罪なことしやがって」

喜瀬川:
「そうかい だったらもっと起請を書いてカラスを皆殺しにしてやりたいねえ」
棟梁:
「そんなことをしてどうする?」
喜瀬川:
「ゆっくり朝寝がしてみたい」
落語 三枚起請オチの朝寝がしてみたいの解説
落語 三枚起請について、最後の部分は少々わかりにくいですが

「三千世界のカラスを殺し 主と朝寝がしてみたい」という都都逸が由来です。
元々遊女と言うのは男性客を騙すのも仕事のうちで、嘘の起請文を書くことも珍しいことではなかったようです。
遊女である私は たくさんの男に偽りの起請文を書いて騙している。そのせいでカラスが死んでしまったとしても、本当に心を許したあなたとは一緒に朝を迎えたい。
色々な解釈がありますが、だいたいこのような意味と思われます。
ただ噺の喜瀬川の場合「女郎は遅くまで客相手に労働しているので 早朝にカラスにカアカア鳴かれると眠れやしないからから迷惑」くらいの意味でしょうか。
落語 三枚起請起請(文)の意味

神仏に誓って自分の言ったことに偽りがないことを表明した証文。元々は武士の間で用いられていたが後に遊郭でも利用されることに
偽りの起請文を書くとカラスが死ぬというのは 起請文を納める紀州熊野神社の使いがカラスであったことからこういわれました。
騙す遊女もいれば約束を守る遊女も
