落語 開帳の雪隠
両国回向院のそばで子供相手に駄菓子屋を営んでいる老夫婦
今は出開帳の真っ最中、町はにぎわっているが、あまりにも混んでいるせいで子供の姿がなく商売にならない
もう一つ頭を悩ますのが、雪隠(せっちん)だけを借りに来る人が多いということ。お婆さんは「雪隠を貸してるだけで商売上がったりだよ」とぼやくが
お爺さんにはどうやら秘策がある様子
お爺さん:
「明日から新しい商売を始めようじゃないか。知らない人の家で頭を下げて雪隠を借りるのは本当は嫌だろう。だったら少し料金をもらって貸せばいい。相手もどうどうと借りられてこちらも儲かる」
さっそく雪隠をきれいに掃除をして「御不浄をお貸しします 一回四文」という立て札を立ててお客を待つ
この計画は功を奏し、四文出せばおおっぴらに借りられるとあって、次から次へと雪隠を借りたいというお客が来る
夫婦は目論見通りに事が運んで満面の笑顔
お爺さん:
「どうだい凄い売り上げだろ」
御婆さん:
「これでこそ御開帳のありがたみがあるねえ」
だがしかし、喜んだのもつかの間で、誰かがうまくいくと誰かが真似をするのが世の常
すぐ先に新しい貸し雪隠が建てられた
建物は新しいし、青竹で囲まれた数寄屋造り、手拭いもきれいでしかも料金は同じ四文
やはり人間 同じ金額で用を足すならきれいなところがいいに決まっている
自然と客足はそちらに流れて 老夫婦の店はまたも商売上がったり
またお婆さんはぼやきはじめる
それでもまたお爺さんには秘策があるようで
お爺さん:
「明日は早く起きてお参りに行ってくるから弁当を作っとくれ
わしが留守の間に店が混むかもしれないから料金の取りっぱぐれがないようにな」
お婆さん:
「はいはい大丈夫ですよ 忙しいことなんてありゃしませんから」
どこかへお参りに出かけるお爺さん
するとお爺さんが出かけた後、次々とお客が押し寄せる
ご飯を食べるまもなくお客の対応に追われるお婆さん
夕方になってクタクタになったところにお爺さんが帰ってくる

お爺さん:
「いや~腰が痛い 売り上げはどうだったいお婆さん」
御婆さん:
「お爺さんもう少し早く帰って来てくれればよかったのに
不思議だねえ、お参りに出かけたら後から後からお客が来て…
神仏のご加護かねえ? どこにお参りに行ってたんだい?」
お爺さん:
「別にお参りになんか行かねえ
向こうの雪隠で一日しゃがんでたんだ」
落語 開帳の雪隠 江戸時代の御開帳について
落語 開帳の雪隠について。
割りと短い噺なのでご開帳についての説明があったり、小話が多数織り交ぜられたりします。
御開帳には単純に普段は公開していない秘仏を自寺で一般公開する居開帳。地方から都市部へご本尊を移動させて公開する出開帳があります。
この噺は出開帳の方で両国の回向院が会場としては有名でした。もっとも賑わったのが元禄五年(1692年)の信州善光寺の出開帳で奉納金品、賽銭など一万二千両(約1億2千万円くらい)の収入があったそうです。
善光寺は今でも7年に一度のご開帳(居開帳)がありますが、その秘仏が江戸で見られるとなると信心深い人だけでなく、野次馬的な人も多く集まったことでしょう。
出開帳に集まる人手を当て込み、茶屋や見世物なども出てかなりの経済効果だったことがうかがえます。
本来、ご開帳は寺社奉行の許可が必要で、開催期間などに様々な規則がありましたが、かなり緩く催された出開帳は700回以上にのぼりました。
回数が多すぎたのか次第にブームは去り、文化文政期(1804年~1830年)以降は見世物や飲食店など娯楽のみが残り賑わったといいます。
その他 仏様が出てくる噺
-
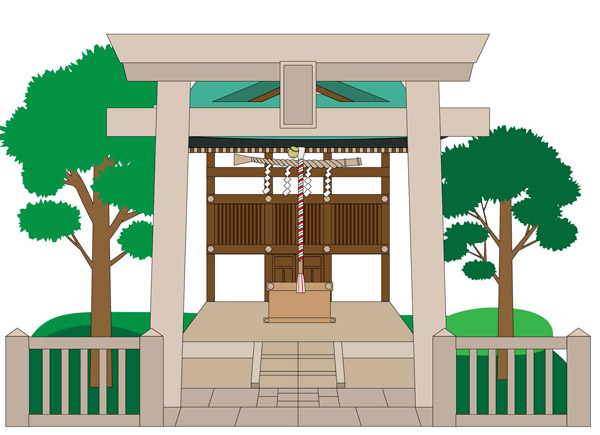
-
落語 心眼のあらすじ 薬師如来(薬師様)のご利益とは?
落語 心眼 按摩の梅喜が目が見えないことを弟に馬鹿にされて帰ってくる 悔しがる梅喜を励ます女房のお竹。梅喜は翌日から薬師様に目が見えるようにと願掛けを始める。 薬師様へ願掛けを始めて21日目の満願の日 ...