落語 紺屋高尾
働き者で生真面目な染物屋の久蔵がこのところ寝込んでしまっている
心配した親方が医者の先生に久蔵を診てもらうよう往診をお願いする。
久蔵がいうには友達に一度だけと誘われて吉原見物に行った際、偶然にも花魁道中に出くわした、その時に見た高尾太夫に一目惚れしてしまった
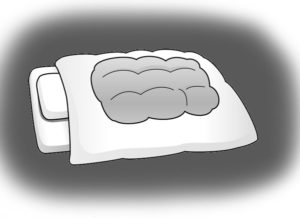
もう一度会いたい久蔵だが、友人の「太夫というのは大名道具といわれるくらいで一介の染物職人のおまえでは相手にもしてもらえない」という言葉に所詮かなわぬ恋と気落ちして床についてしまったのだという
要は恋煩いということ。久蔵の告白を聞いて遊び好きの血が騒いだ先生、一肌脱ごうと一計を案じる
先生:
「なあに大名道具とはいうものの筋さえ通せば職人だろうがなんだろうが会えないわけじゃない。おまえが一生懸命働いて、三年分給金を貯めれば私が手回しして、必ず会えるようにしてあげよう」
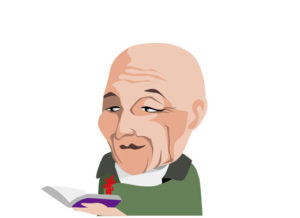
名医というものは恋の病も治すという、先生の会わせてやるという言葉を聞いて久蔵は全快し前にも増してまじめに働きはじめた。
そして三年が経ったある日
親方:
「久蔵おまえはこの三年よく働いたな。ただよく考えてみろ三年も努力した金をたった一晩のためにつぎ込むのは惜しい話だ。おまえはまじめで腕もいい、もう少し頑張れば暖簾分けしてやるから、貯めた金で自分の店を持つといい」

久蔵:
「親方このお金はどうあっても高尾太夫との初会のために使うと決めてたんで…」
親方:
「そうかおまえのその心意気には言葉もない」
ついに念願の日を迎えた久蔵。衣装を整え、先生からは
先生:
「染物職人ということは隠して流山あたりの若旦那ということにしなさい、いらないことを言わないように」
とアドバイス
その後、先生の口利きによってとうとう初会を果たすが、慣れないお大尽言葉を無理に使おうとするのでなんとなくチグハグやり取り

三年待って本懐をとげた一夜が明けると高尾大夫が
高尾:
「今度はいつきていただけますか?」
久蔵:
「あと三年待っておくんなさい」
高尾:
「あれ、三年も?」
久蔵はもし高尾太夫が身請けでもされれば、これが今生の別れと思うと感極まって、涙ながらに自分の素性とここに至った経緯を話し始めた
それを聞いた高尾太夫は職人風情と見下すどころかそっと涙を流してつぶやいた
高尾:
「なんと三年もの間…来年二月の十五日に年季が明けます。その時になったら訪ねて行きますから夫婦になってくれますか」
もちろんうれしくて夢か現実かもわからなくなる久蔵 年が明けて迎えた二月十五日 約束のその日がやってきた
店の若い衆は吉原の太夫が?こんな町人地へ?と半信半疑
親方も「久蔵おまえも若いな だが仕事に張りが出るなら問題ないやな」と半笑い
そこへ駕籠に乗ってやってきたのは、町人の女房風の身なりをしているがまぎれもなく高尾大夫。

久蔵との約束を守ったのだ
高尾:
「ふつつかな者ですが、久蔵様ともども宜しくお願いします」
その後久蔵は高尾と夫婦になって独立して店を構え 江戸中の評判となり店は大変繁盛したという話
落語 紺屋高尾 遊郭で使われた廓言葉について
落語 紺屋高尾について。
吉原の花魁、遊女は江戸の出身というものばかりではありませんでした。東北の農村出身の者も多くその地方の訛りを隠すために廓言葉というものがありました。
よく耳にするのが「ありんす」「ざます」のようなもの。
地方から出てきて、親兄弟のために遊里で客を取っているということを江戸の人々は理解していたため、吉原の花魁たちを蔑むような傾向はなかったといいます。
落語 紺屋高尾余談 高尾太夫という名前について
高尾という名前は吉原の大見世の一つ三浦屋で代々受け継がれた遊女の最高ランク。
代々襲名制で仙台高尾は伊達綱宗が入れあげた傾国の美女として有名です。その後綱宗は危機感を感じた家臣によって21歳で隠居させられています。
女郎の誠と卵の四角、あれば晦日に月が出る
といいあらわされるように遊女は誰にでも「惚れた」や「年季が明けたら夫婦になってください」と言いました。それを真に受けて身を持ち崩した男性も多かったと言います(というか現代でも似たようなものか(笑)
こういう典型的な遊女は品川心中や三枚起請といった噺に登場しますが、紺屋高尾に登場する高尾太夫は少し庶民の願望も含まれていると思われます。
※もちろん落語なのでファンタジー上等ですが^^;
-

-
落語 三枚起請のあらすじ オチの朝寝がしてみたいの意味と起請文とは?
落語 三枚起請 吉原の花魁にいれこんでいる猪之(いの) それを棟梁が「本気になるなと」釘を刺すが、猪之は「俺だけじゃなく相手も本気だ」と言い張る その証拠に年期があけたら夫婦になるという誓いの言葉を書 ...
-

-
落語 品川心中のあらすじ 心中失敗 実際に生き残った方はどうなる?
落語 品川心中 品川の遊郭白木屋で売れっ子だった遊女のお染だが、寄る年波には勝てず、最近では客がめっきり減ってしまう。 自分より若い遊女にどんどん客が付き、お茶を挽く日が増えていくことにため息の出ない ...