落語 ねずみ
江戸時代の名工左甚五郎が旅の途中でフラリと宿場町を訪れた。そこで宿を探していると、子供の客引きに声を掛けられる。
宿の名前はねずみ屋で着いてみるとなるほど名前の通り粗末な小屋のような造り。
対してその向かい側には虎屋という立派な宿屋があり、こちらのボロさを際立てている。
主人に聞くところによると、元は自分が虎屋の主人だったが、怪我をして養生している間に番頭に店を乗っ取られ、女房もあちらに行ってしまった。
仕方なく虎屋が物置として使っていた建物を宿屋にしてなんとか暮らしているという。
それを聞いた甚五郎はなんとかしてやろうとコツコツと何かを彫り始めた。
そして出来上がったのが見事なネズミの彫刻。
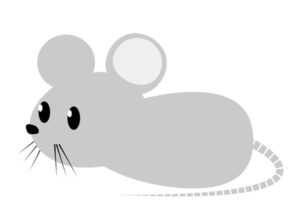
甚五郎:
「それをタライに入れて店の前に置いておきなさい」
子供が言われたとおりに置いておくと、なんとネズミがタライの中を走り回りそれが評判となって大繁盛。
それを見届けた甚五郎は再び旅に出る。
一方そのあおりで客を取られて面白くないのが向かいの虎屋の主人。
自分のところも名工に頼んで、向こうがネズミならこっちは屋号の虎だと、虎の彫り物を作らせる。
それをネズミを睨むように宿の前に置くと、ネズミが動かなくなり、元の彫り物に。
この話を風の噂で聞いた甚五郎は再びネズミ屋を訪れて、動かなくなったネズミに話しかける。
甚五郎:
「おまえはあんな虎が怖いのか?大した出来でもないようだが」
するとネズミが動き出して
ネズミ:
「ああ、あれは虎でしたか。私は猫かと思ってました」
落語 ねずみ名工左甚五郎は実在しなかった?
落語 ねずみについて。
名工として名高い左甚五郎。この噺は落語なのでもちろんフィクションですが、実は存在自体が疑問視されています。
ちなみに出身地もはっきりしてせず、生没年不詳。甚五郎作と伝えられる彫刻は日本全国100箇所にも及びます。
もっとも有名な作品、日光東照宮の眠り猫ですが、東照宮が現在のような豪華絢爛に改装されたのが、1636年(寛永13年)それ以前の安土桃山期から江戸後期までの300年間に渡って左甚五郎作と伝えられる作品が残されており、一人ではなく名工の代名詞だったとも考えられています。