落語 長屋の花見
ある日貧乏長屋の住人達に大家さんから呼び出しがかかる。
誰もまともに家賃なんて払ってないからきっとその催促だ
場合によっちゃあいよいよ追い出されるのかと長屋の住人達は戦々恐々としながら大家さんのところへ
すると意外なことに大家さんからの呼び出しの理由はこのようなことだった
大家:
「うちの長屋は世間から貧乏長屋、貧乏長屋と呼ばれて景気が悪くってしかたがない。
今日はみんなで花見にいって陽気に騒いでひとつ貧乏神を追い出そうじゃないか
もちろん酒や肴はこちらで用意したから安心しとくれ。
このとおり一升瓶にこの重箱の中にはカマボコと卵焼きが入ってる
なあに心配するなみんなわたしのおごりだよ」

大家さんの意外な提案に長屋の住人は大喜び、さっそく上野の山へ向かうことになった。
上野の山に着いてみんなでさあ盛り上がろうというところで大家さんの種明かし
一升瓶の中身はお酒ではなく番茶を煮出して薄めたもの
カマボコは大根のコウコと卵焼きの正体は黄色いタクワン
住人:
「さすがは貧乏長屋の大家さんだ これじゃあガブガブのボリボリだよ」
大家:
「まあいいじゃないか。こっちが気分良く盛り上がれば周りから見たら酒盛りしてるように見えるさ」
妙なパフォーマンスに付き合わされることになった住人達は楽しそうに振舞うのに四苦八苦
住人「じゃあお茶…じゃなかった酒をついでくれ おっとっと!おうそんなについで俺に恨みでもあんのか」
大家:
「さあさあ熊さん玉子焼きを食べとくれ」
熊:
「すいやせん 最近歯が悪いもんで」
大家:
「卵焼きを食べるのに歯なんて関係ないだろう」
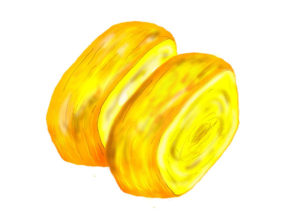
大家:
「八つっあんもカマボコをおあがんなさい」
八:
「へえ 私はこれをしょっちゅう食べてまして。細かく刻んで刺身の添え物にもしますし、腹の具合が悪いときなんかカマボコおろしにいたしやす」
大家:
「カマボコおろすなんて、そんなやつがあるかい」
と中身がニセモノなだけになんだかチグハグ
そこへ住人の一人が
住人:
「大家さん大家さん、近々この長屋にいいことがありますよ」
大家:
「どうしてだい?」
住人:
「茶碗の中に酒柱が立っております」
落語 長屋の花見江戸時代の花見スポット

江戸の桜の花見スポットで有名だったのは上野の寛永寺、飛鳥山、御殿山、墨堤(隅田川)でした。
しかし上野の寛永寺の桜は三代将軍徳川家光が天海僧正のために植えた由緒正しい桜だったので、境内での飲食や鳴り物などは禁止されており、静かに風流に見るしかなかったそうです。
(当時の寛永寺は今と比べ物にならないほどの敷地面積でした)
長屋の熊さん八つっあんのような住人達にとっては退屈な場所ではなかったでしょうか。
桜というと現代ではソメイヨシノが思い浮かびますが、江戸時代にはなく明治に入ってから今のように植えられ始めたため、長屋の花見に出てくるのは彼岸桜だったと考えられます。
桜の開花には時間差があり、上野の彼岸桜を見たら今度は谷中の枝垂れ桜、御殿山の八重桜と各地の桜を見て歩き江戸の人々は春を満喫したと言われています。