落語 錦の袈裟
町の兄貴分が若い衆を集める。なんでも隣町の若い衆が揃いの縮緬の長襦袢で吉原に繰り出し大変な評判になったという。そんなものには負けてられないから、こっちも派手な趣向で吉原に繰り出そうという相談だ。

あれこれ相談しているうちに一人が錦で揃いの褌(ふんどし)を作りかっぽれを踊ろうと提案する。
錦なんて贅沢な布を惜しげもなく褌に使うなんてこれは誰でも驚くし、隣町の若い衆も真似できないだろう。計画実行 明日の晩までにそれぞれが錦の褌を用意しようということになった。
これに困ったのがいつも若い衆の端っこに加わっている与太郎。とても錦の褌なんて用意できそうもない。仕方がないので女房に相談すると
女房:
「お寺には錦の袈裟があるからそれを借りてきな。親戚の娘に狐が憑きましたので袈裟を掛けて狐を払いたいのでお借りしたいと言えばいい」
与太郎は女房の言うとおりお寺へ行き、言われたとおり袈裟を貸してくれるよう和尚にお願いする

和尚:
「そういう訳なら貸してやりたいのだが、明日その袈裟を寄付してくれた檀家の法事があるので その時に袈裟がないと具合が悪い」
与太郎:
「明日の朝までには必ず返します」

しぶる和尚をなんとか説得して袈裟を借りて帰り いざ吉原へ。だがお寺の袈裟だけに褌にしてみると、いらないものがたくさん付いている。
町の若い衆は吉原で飲んで騒いだ後、裸になって、かっぽれを踊り始める。これには店のものもあまりの派手さに驚いた
遊女1:
「この方たちはきっとお忍びで来た殿様の一行に間違いないよ。中でもあの変わった形の褌の方、あれが殿様だね」
遊女2:
「でもあの人が一番ボ~っとしてますよ」
遊女1:
「そりゃあ殿様だもの悩みがないから自然と呑気な性格になるのさ」
遊女2:
「殿様の褌の前についている輪はなんでしょうね」
遊女1:
「あれは厠で的を外さないように通すチン輪よ。とにかく御付きの者よりも殿様を大事にするのよ」
勝手に勘違いされたおかげで与太郎だけがモテて他は全員振られてしまって面白くない。

翌朝、花魁と寝ている与太郎を置いて先に帰ろうとする若い衆たち
与太郎はそれを追いかけようとするが、花魁が手を離してくれない
花魁:
「お殿様 けさは返しませんよ」
与太郎:
「袈裟は返さないって?それじゃあ和尚さんに怒られちまう」
落語 錦の袈裟法事に着る袈裟の種類と寄付する人(檀那)について
落語錦の袈裟について。
オチは翌朝までに返すと言ったのに袈裟(今朝)返さないと約束を破ってしまうという「袈裟」と「今朝」を掛けたもの。
噺に袈裟が登場しますが、袈裟といっても様々な種類があり、主なものだと五条袈裟、七条袈裟、輪袈裟などがあります。
輪袈裟は肩から掛けるだけのものなので、短く褌として締めるには向きません。五条袈裟も金欄の布を使いますが派手さには欠けます。褌に使われたのは七条袈裟ではないでしょうか?大きすぎる気もしますが…
噺の中で和尚さんは法事に着て行くと言っていますが、七条袈裟を着て行くというのは少々大袈裟かもしれません^^;お寺で行われる結構大きな儀式用のイメージがあります。
※寄付をしてもらった檀家さんということなので、着て行くのもありなのでしょうか?
ちなみに檀那(旦那)の語源はサンスクリット語のダーナの音写(漢字に当てはめること)からきておりお布施と訳されました。
変化して寺を支える人を檀家と呼ぶようになり、檀家はお布施などの寄付金で自分の菩提寺(檀那寺)を支えます。
七条袈裟を今注文しようとするとカタログ価格200万円~だそうです。袈裟を寄付してくれた檀家さんはかなりの大旦那と言えそうです。
その他 お寺が登場する噺
-
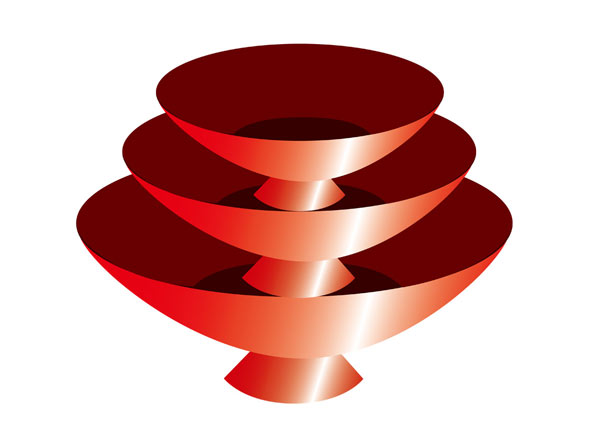
-
落語 転失気(てんしき)のあらすじ 転失気とは医学用語?
落語 転失気(てんしき) お寺の和尚さんの体調がここ最近すぐれない。お医者さんを呼んでみてもらったところ。 医者: 「熱はそれほどないようですし、少々お腹が張っとるようですな。てんしきはありますか?」 ...
-

-
落語 万金丹のあらすじ 江戸時代の薬について
落語 万金丹 旅の途中で路銀が尽きて行き倒れ一歩手前の辰五郎と梅吉 道に迷い「こんな知らないところで野宿か」と困っているところに 天の助けかお寺を見つける 寺の門をたたくと今晩は泊めてもらえることに。 ...