落語 あくび指南
町内にできた「あくび指南」の道場の看板を見て、新しいもの好きの男が興味を持つ
ただ一人で行くには心細いので友人に声を掛ける
友人:
「あくびだなんて そんな待ってりゃ勝手に出てくるものを習う ましてや金を払おうなんてくだらねえ俺はお断りだ」
男はしつこく友人を説得し、とうとう友人は見ているだけという条件で一緒に道場の門をくぐることとなった。

先生:
「お友達は見学ですね。いいでしょうでは初歩からお教えします。まずはお手本から」
あくびなんて誰がやっても同じものだと思いきやそうでもないらしい、夏の大川(隅田川)で舟遊びをしている設定で先生があくびをしてみる
先生:
「たまには舟もいいが、ふぁ~あ退屈でならねえ」
男は先生の手本通りにしているつもりでも、先生から細かいところに指導が入る
先生:
「一杯やった後、船に揺られているつもりで身体を少し揺すってください。もう少し気だるい様子でお願いしますよ」

先生が根気よく教えるが、なかなかうまくいかない男はだんだんあくびとは関係のない話をし始める
先生:
「こんな不器用な人ははじめてだ」
友人もだんだん退屈になってきて
友人:
「こんなくだらねえことに付き合わされてる俺の身にもなってくれよ。ふぁ~あ退屈でならねえ…」
と大あくび
そこで先生が
先生:
「あ、お友達の方が筋がいい」
落語 あくび指南江戸時代人気のあった習い事とは
落語 あくび指南について。
江戸時代天下泰平の世の中になると人々が趣味や習い事をする余裕が出てきました。町内には様々な習い事の稽古場があり、学問系だけでなく歌や踊り、剣術道場 変わったものでは喧嘩の仕方というものもあったそうです。

人気があったのがジャンルを問わず年頃の女性の先生がいた習い事。(長唄の先生は女性が多かったとのこと)
先生を目当てに男の弟子が集まり、先生が結婚してしまうと潮が引いていくようにみんなやめてしまったそうです。
江戸の男女比率は後期になれば改善されますが、男余りの状態だったようで、吉原はともかく素人の女性と知り合う機会がなかったためと考えられます。
なんとも江戸っ子らしくさっぱりしているというか、げんきんというか^_^;のどかな様子が想像できます。
女性の長唄の先生が出てくる噺
-
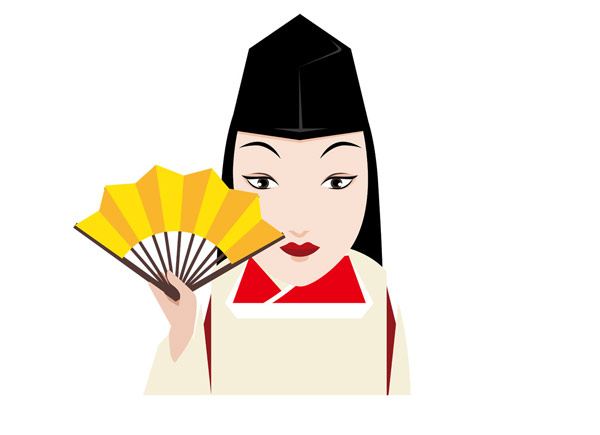
-
落語 猫の忠信のあらすじ オチと義経千本桜のパロディー部分を解説
落語 猫の忠信 次郎吉が長唄の稽古に行こうと同じ長屋に住む六兵衛を誘いにくるが 六兵衛はもう馬鹿馬鹿しくて行く気がないという。 なんでも長唄の女師匠が男と仲良く酒を飲んでいるのを目撃してしまい、その男 ...