落語 お血脈
信州の善光寺にはありがたい「血脈の印」というものがある。
これを額に押してもらうと、どんな罪業深重な者でも極楽へ往生できるというありがたい印
人にはその大小にかかわらず、誰にでも生前犯した罪というものがあるが、誰だって地獄になんて行きたくはない。
だから我も我もと善光寺に人が押し寄せて、印を戴いたものだから、みんな極楽へ行ってしまい、地獄は閑古鳥が鳴き出した。
仕事がないから鬼たちは金棒を売ってしまうし、その熱いことで有名な地獄の釜だって薪を買う金がないから温いまま。
地獄の閻魔大王は困ったが責任を取って辞職するわけにもいかない。自分は唯一無二の閻魔大王代わりはいないからだ。
閻魔:
「いまいましい血脈の印め。こうなったらこの諸悪の根源 血脈の印を善光寺から盗み出すしかない」
幸いにも地獄には歴代の泥棒がそろっているから誰にやらせようか閻魔大王は思案する

閻魔:
「鼠小僧は大名屋敷専門だし盗むのは千両箱じゃないから嫌がりそうだ。外国人に頼んでも寺のことはわからないだろう
そうだ石川五右衛門!あいつがおった。あいつなら豊臣秀吉の寝所に忍び込んだ実績がある。そうだ!あいつがいい」

閻魔大王からの命を受け信州善光寺に向かった石川五右衛門夜陰に乗じて本堂に忍び込む。
見張りの多い城に忍び込んだほどの腕前だからお寺に忍び込むくらい造作もない
やがてお血脈の印を発見して持ち出すが、さっさと地獄へ帰ればいいものを南禅寺の屋根でやったパフォーマンスを善光寺でもやってしまう
「絶景かな絶…」
額にお血脈の印を押し戴いたものだから、そのまま極楽に往生してしまった
落語 御血脈石川五右衛門は実在したのか?
落語 お血脈について。

大泥棒といえば思い浮かぶのが石川五右衛門ですが、その存在自体が疑問視されていました。近年、宣教師の日記の中にわずかに注釈があり、その存在を伺わせるものも発見されています。
しかし他にはっきり石川五右衛門と登場するのが林羅山の「豊臣秀吉譜(1641年)」で上記の宣教師の日記から半世紀の開きがあり、まだまだ謎は多いと言えます。
※はっきりしているのが京都、堺、伏見を荒らしまわった盗賊の頭領が死刑になったこと
出自は浜松の出身であるとか、伊賀で忍術を習い天正伊賀の乱で仲間を失い織田信長や豊臣秀吉に恨みを持っていた、秀吉の寝所に忍び込んだ際、千鳥の香炉が鳴いたため侵入したのがばれてしまった等多彩です。
歌舞伎や浄瑠璃に取り上げられ正体不明の大泥棒ということで、次々と今に伝わるエピソードが作られていったものと考えられます。
その他架空の人物?が登場する噺
-
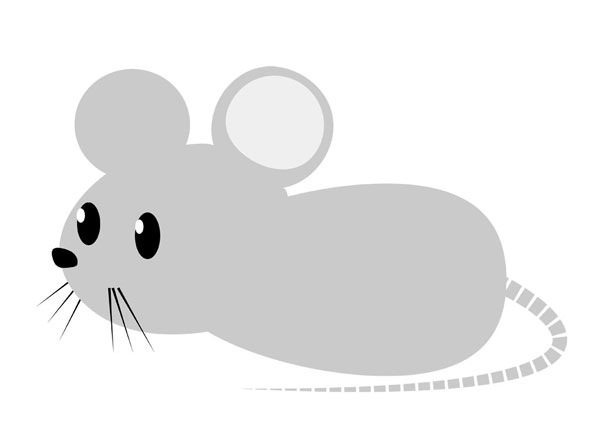
-
落語 ねずみのあらすじ 左甚五郎は架空の人物?
落語 ねずみ 江戸時代の名工左甚五郎が旅の途中でフラリと宿場町を訪れた。そこで宿を探していると、子供の客引きに声を掛けられる。 宿の名前はねずみ屋で着いてみるとなるほど名前の通り粗末な小屋のような造り ...