落語 やかん
ご隠居の家へ店子の熊五郎が遊びに来る。二人とも暇人だ。
熊五郎は浅草の観音様に行ってきた帰りだという。しかしご隠居は
ご隠居:
「浅草の観音様というのは通称で 本当の名前は金竜山浅草寺という。祀られているご本尊は…」

蘊蓄を語るご隠居の博識ぶりに感心する熊五郎
ご隠居はおだてられて「森羅万象なんでも聞きなさい」なんてことを言ってしまうものだから、熊五郎の質問攻めが始まってしまう
熊:
「ヒラメっていう魚はどうしてヒラメって言うんですか?」
ご隠居:
「平たいからヒラメだ」
熊:
「ではカレイは?」
ご隠居:
「カレイは家令と書く。ヒラメの家来だからな。」
熊:
「鰻を焼いたやつはどうしてカバ焼きって言うんですか?」
ご隠居:
「鰻にタレをつけて焼いてみるとバカに旨い じゃあバカ焼きにと思ったがひっくり返さないと焦げてしまう。だからひっくり返してカバ焼きだ」
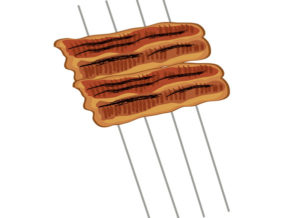
次第に目についたものを手当たり次第に聞き始める
熊:
「じゃあ土瓶は?」
ご隠居:
「土で出来ているビンだから土瓶、鉄で出来ていたら鉄瓶だ」
熊:
「じゃあ やかんは?矢で出来てるからですか?」
ご隠居:
「あれは以前は水沸かしと呼ばれていたのだが 川中島で武田軍と上杉軍がにらみ合った時…」
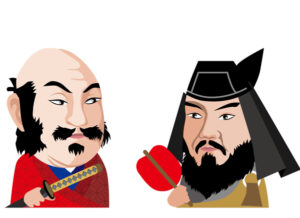
熊:
「今やかんの説明を聞いてるんですよ」
ご隠居:
「だから そのやかんの話だから黙りなさい!
両軍 川を挟んでにらみ合ったがいっこうに決着がつかない
ところが嵐の夜 今日は戦いもないだろうと油断している武田軍に上杉軍が夜襲をかけた

油断していた武田軍は大混乱!その時一人の若侍が跳ね起き鎧を身に着けるが
兜が見当たらない ふと脇を見ると大きな水沸かしが!この水沸かしの水をザ~っと空けると
頭にかぶり馬にまたがり槍を振りかざしただ一騎で上杉軍の中へ討って出た
若侍に向かって上杉軍から矢が雨のように降ってくる しかし矢が水沸かしに当るたびに
矢が当ってカ~ン、矢がカ~ン、矢カ~ンでやかんになった」

熊:
「ずいぶん手間がかかりましたね。でも頭にかぶったらツルが邪魔でしょう?」
ご隠居:
「ツルはアゴにかける」
熊:
「湯をさすときの口が片方にあって変ですが?」
ご隠居:
「口がない方を枕を使って寝る時に下にするんだ」
落語 やかんご隠居が説明したワードについて
落語 やかんについて
矢がカ~ンでやかんの部分で終わるパターンも多いこの噺
ご隠居の説明がすべて知ったかぶりかというと そうではなさそうで、ヒラメは平たいから鮃(ヒラメ)というのはもしかしたら正解かもしれません
鰈(カレイ)は昔「カラエヒ」と言ってエイの仲間だと考えられていて、「カラ」の部分は枯れる、つまり枯れた葉のような色をした「エイ」これが変化して鰈(カレイ)となったと考えられるそうです。
※ご隠居のこじつけのようですが、一応調べました笑
ちなみにカレイ(家令)とは皇族、華族の家で主人に代わって事務会計や雇い人の管理をした人です。このワードが出てくるということは明治時代以降の噺ということでしょうか。
カバ焼きは串に刺したその姿が「蒲の穂(がまのほ)」に似ていることから蒲焼(かばやき)や色や形が樺の木に似ているからとか諸説あります。
やかんは元々「薬鑵」と書き、薬を煎じるのに使われていたものが次第に変化して薬缶(やかん)となったそうです。
もちろん「矢カ~ン」でやかんではありません。
