落語 浮世根問
長屋の熊五郎がご隠居の元を訪ねてくる
なにやら聞きたいことがあるという
何を聞きたいかと思えば「お天道様が暑くてかなわないから 退かせる方法はないか?」という

もっとまともなことを聞きなさいとご隠居が嗜めるが 後から後から出てくる変な質問…
熊:
「婚礼のことを嫁入りって言いますが何でですか?」
ご隠居:
「それは簡単なこと 目が男に二つ女に二つ合わせて四つだから四目入り(よめいり)だな」
熊:
「じゃあその日から奥さんって呼ぶのは?」
ご隠居:
「奥の部屋でお産をするから奥さんだ」

ご隠居の回答もかなりあやしいがやり取りは続く
熊:
「人間死んだらどうなりますか?」
ご隠居:
「極楽浄土で仏になる」

熊:
「極楽ってのはどこにありますか?」
ご隠居:
「地獄の隣だよ」
熊:
「じゃあ地獄はどこに?」
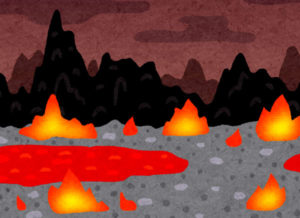
こんな調子で質問を繰り返すから段々面倒になってくるご隠居
ご隠居:
「極楽の隣だ」
熊:
「じゃあ極楽は?」
ご隠居:
「いいかげん もう帰りなさい」
「極楽の場所がわからない限りここを動かない」と座り込む熊五郎
ご隠居は仕方がないので熊五郎を仏間に連れていく
仏壇を指差して

ご隠居:
「ここが極楽だ 死んだらみんなここで仏になる」
熊:
「みんなってことは鶴や亀もここで仏になりますか?」
ご隠居:
「いやあれはならない よく見なさい このとおり

ろうそく立てになっている」
落語 浮世根問オチの蝋燭立てになっているの意味
落語浮世根問いの解説
鶴亀のろうそく立ては現代では主に浄土真宗の大谷派(東本願寺)や高田派などで用いられます。
浄土真宗は関西東海北陸に多いそうなので地域によってはわかりにくいオチになりそうです。
同じ浄土真宗でも本願寺派(西本願寺)は鶴亀のろうそく立てを使わないそうです(ややこしい)

ちなみに実家が東本願寺なのでお寺さんに「ろうそく立てが鶴亀の形をしているのはどうして?」と小さい頃に聞いたことがあります。
その回答が「二本足の鶴、四本足の亀が同じところに仲良くいる これが阿弥陀様の前ではみんな平等だということを表している」だそうです。
…でも今考えるとご隠居的な適当回答で煙に巻かれたような気もしてきました(^^;
その他のご隠居と若者の珍妙なやりとりの噺
-

-
落語 やかんのあらすじ 薬缶その他語源とは?
落語 やかん ご隠居の家へ店子の熊五郎が遊びに来る。二人とも暇人だ。 熊五郎は浅草の観音様に行ってきた帰りだという。しかしご隠居は ご隠居: 「浅草の観音様というのは通称で 本当の名前は金竜山浅草寺と ...
-

-
落語 つるのあらすじ 江戸時代鶴は食用にされていた?
落語 つる ご隠居の家に遊びにきた八五郎。今日も今日とて馬鹿話をしている そのうちこの間見た鶴の掛軸の話になり 八五郎: 「ご隠居 鶴はなんでつるって言うんですか?」 という話になる するとご隠居は ...