落語 粗忽長屋
そそっかしい八五郎が浅草の観音様にお参りした帰り道 人だかりが出来ているのに出くわす

聞くところによると行き倒れが出たとのこと 野次馬丸出しの八五郎は人だかりを押し退けて前の方へ
「ごめんよごめんよ~」と先頭に来くると行き倒れの遺体を見てびっくり
八:
「なんてこった!こいつは兄弟分の熊五郎です。こんなことになっちまって…」
現場を仕切っていた役人は 遺体の身元がわかってひと安心 引き取ってもらうつもりだったが 八五郎がおかしなことを言い出す
八:
「遺体は本人に引き取らせますから」
「何を言っているんだ?」役人が止める間もなく長屋へ帰ってしまった
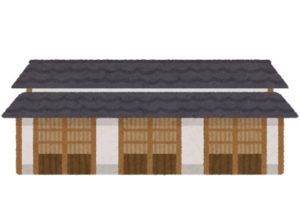
長屋へ帰り寝ている熊五郎を叩き起こすと
八:
「熊!浅草でお前が死んでたぞ!」
熊五郎の方も昨晩飲みすぎて どうやって長屋へ帰ってきたか記憶がないので「それは死んだからに違いない」という風に話がまとまってしまう
熊:
「俺は死んだのか…もっと旨いものを食っとけばよかった…」

泣き出す熊五郎 二人は遺体を引き取るために浅草へ向かう
八:
「行き倒れ本人を連れて来ました!」
変な人が一人増えたと困り顔の役人をよそに 遺体にかけられている莚(むしろ)をめくってみる二人
「俺にしては顔が長い」という熊五郎だったが夜露に当たったからだとまたしても納得させられてしまう

「手厚く葬ってやろう」と遺体を引き取ろうと二人で抱き上げたところで熊五郎が呟く
熊:
「抱かれているのは俺なんだけど、抱いている俺は一体誰なんだ?」
落語粗忽長屋江戸のアーバンライフ 長屋暮らしについて
長屋と聞くと貧乏長屋を思い浮かべてしまいがちですが、現代のアパートやマンションのようにランクがありました。
家賃は安い長屋 いわゆる裏長屋で300文(約7500円)高級長屋で1000文(約25000円)くらいと言われています。
基本的な広さは幅奥行で九尺二間で六畳一間で入り口には土間やかまどがあるため、生活スペースは四畳半ほどしかなく、ここに家財道具を置き、家族で住んでいたというから驚愕の狭さです。
ちなみに長屋の住人を町人とはいいますが、彼らは公的には町人とはみなされず、大家さんの居候という扱いでした。
そのため税金の支払い義務はなく、収入に対する家賃の安さから意外とのんびりと暮らしていたのかもしれません。
税金を払わなくていいって!現代人から見たらうらやましい限りですが、公共のサービスなんて比べ物にならないくらい貧弱だったろうし…
どうなんでしょう?
裏長屋からのサクセスストーリー芝浜 落語 芝浜 腕前はいいのだけど、酒ばかり飲んで何日も仕事に行っていない魚屋の勝五郎 女房は暮れも押し迫って正月を迎える金もないからと朝から勝五郎をたたき起こし、家を追い出して仕事に行かせた。 しかし芝 ...

落語 芝浜のあらすじ 江戸時代財布をネコババしたら
長屋と言えば思い浮かぶこの噺
-

-
落語 長屋の花見のあらすじ 江戸時代の桜の種類とは
落語 長屋の花見 ある日貧乏長屋の住人達に大家さんから呼び出しがかかる。 誰もまともに家賃なんて払ってないからきっとその催促だ 場合によっちゃあいよいよ追い出されるのかと長屋の住人達は戦々恐々としなが ...