落語 夏の医者
病気になった父親のために息子が医者を呼びに行く
しかし一番近くの医者でも山を越えて六里半
やっとのことで医者の元にたどりついたが、医者の先生は人の命を預かる職業の人にしては、ややのんびりしているのが気になるところ
息子が「父親が苦しんでいて急いでいる」ということを告げるとようやく薬箱を用意して出発した
医者:
「では私の知っている近道を行こう 難所ではあるが病人のためだ」

医者の言う道は行きより近いが草木が生い茂り険しい道。疲れたから一服しようと二人で腰掛けたところで、急に辺りが暗くなる
息子が何事かと慌てていると
医者:
「そういえばこのあたりで うわばみ(大蛇)が出ると言う噂を聞いたことがある」
息子:
「ではここはその腹の中ですか?」
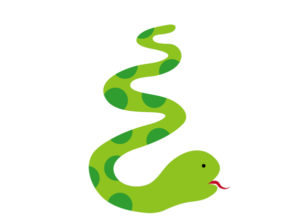
「このままでは腹の中で溶けてしまう」とうろたえる息子だったが、医者は落ち着いている。
医者:
「では 下剤を調合しよう」
腹の中で下剤をバラ撒くとうわばみは苦しみ、やがて二人を尻の穴から外へドバ~
なんとか助かったと嫌な臭いをさせながら 苦しむ父親の元へ
医者がどれどれと診察を始めると、父親は萵苣(チシャ)を生で食べたという
医者:
「これは食中毒。萵苣(ちしゃ)に当たったようだな。夏のチシャは身体に悪い」
しかし さっそく薬を調合…と思ったところで薬箱をうわばみの腹の中に忘れてきたことに気がついた
返してもらうよりしょうがないと、医者は再びうわばみのところへ
道を戻るとうわばみは下剤が堪えたと見えて大分弱ってぐったりしている
医者:
「いたいた おい薬箱を取りたいんだ もう一度飲んでくれないか?」
うわばみ:
「そうはいくか夏の医者は身体に悪い」
落語 夏の医者夏のチシャはなぜ身体に悪い?
落語 夏の医者について
最後の「夏の医者は身体に悪い」はチシャと医者をかけたダジャレ落ち
そもそもチシャ(萵苣)って何でしょう?チシャとは広い意味でレタスの仲間です。夏のチシャということはサニーレタスと言えるのではないでしょうか。
江戸時代にレタス?なんだか不思議な感じがしますが、実はレタスは中国から平安の頃に伝わっており、この頃はお馴染みのボール型のものではなく葉っぱだけのものが栽培されていました。

落語 夏の医者そもそもなぜ夏のチシャは身体に悪いのか?
江戸時代 野菜の食べ方は漬物にしたり、煮物にしたりで生野菜を食べる習慣がほとんどありませんでした。栽培に下肥が使われており、寄生虫や雑菌にあたるリスクがあったのが大きな理由です。
夏の萵苣(チシャ)は身体に悪い…上記の理由に加えて生野菜を食べるのは暑さで葉も傷んでいる可能性もあり、夏はとくに食べない方が無難でしょう。
ちなみに生野菜を食べる概念が伝わったのは明治に入り西洋料理が紹介されたあたり。といってもサラダにドレッシングで庶民が食べるようになるのはもう少し先のこと。
戦後GHQの政策により畑に撒く肥料が下肥から化学肥料等寄生虫のリスクの少ないものに切り替えられてからだと言われています。
その他大蛇が登場する噺
-

-
落語 そば清のあらすじ オチと江戸時代に残る大食い記録について
落語 そば清 そばなら何杯でも食べることができると豪語する旅商人の清兵衛 その見事なそばの食べっぷりからついたあだ名は「そば清」 本業の傍ら、そばの大食いで賭けをして小銭を稼ぐのが日課となっている。 ...