落語 干物箱
遊んでばかりなのを懲らしめようと、大旦那は息子の徳三郎を店の二階に軟禁してしまう。
二階に閉じこもって3日が過ぎた。徳三郎はさすがに外にも出たいし、遊びにも出かけたい。
徳三郎は「風呂に行かせてくれ」と大旦那に頼みこみ、なんとか「半刻だけ」という約束で二階から出ることを許された。
さて外に出てはみたものの、半刻だけでは本当に風呂に行って帰るだけ。遊びに行くならもう少し時間がほしい。
そこで友人の与太郎に身代わりを頼むことを思いつく。与太郎の特技は声真似で、徳三郎の声もそっくりにマネできる。
徳三郎は与太郎に小遣いを渡し、

徳三郎:
「下から父親に話しかけられても俺の声真似でごまかしてくれ。なあに二階に俺がいることさえ確認できれば二階に上がって来ることはあるまいよ」
と言いつけると遊びに行ってしまった。
与太郎オドオドしながら徳三郎の家に入ると「ただいま戻りましたと」大旦那に一声かけ、顔を合わせることなく二階へ上がりこむ。
大旦那はこういう時に限って何かと二階へ向かって声をかけてくる。
大旦那:
「今日頂いた干物はどこにおいた?」

そんなことは打ち合わせになかったので
与太郎:
「干物箱にしまっておきましたよ」
大旦那:
「干物箱なんてどこにあるんだ?ねずみに齧られるといけないから持ってきてくれないか?」
最初はごまかしていた与太郎だったが、二階へ来そうになる大旦那に向かって「風邪を引いてしまったようです」この一言がよくなかった。
大旦那が薬を持って上がってきてしまい計画はすべてばれてしまう。
そこへちょうど財布を忘れたことに気が付いた徳三郎が帰って来て
徳三郎:
「おい 与太 財布をそこから放ってくれ」

外から二階へ向かって声をかける。
それを聞いた大旦那は
大旦那:
「徳三郎!おまえなんかもう帰ってこなくていい!」
徳三郎:
「さすがは与太 親父の声もそっくりだ」
現代でいうモノマネ「声色」
大旦那がお座敷で飲んでいると、隣の部屋から息子の徳三郎の声が聞こえる。「また遊んでいるのか!」と隣の部屋に怒鳴り込んだところ、声の主は与太郎だった。こういう場面が入ることもあります。
声真似についてですが、娯楽の少なかった江戸時代、色々な習い事があったことは以前紹介しました。「声色(こわいろ)」と呼ばれる声帯模写を教える道場もあったそうです。
基本的には人気のある歌舞伎役者の声だけではなく、身振り手振りなどもセットで習い、芸に自身のあったものは木戸銭をとって商売にしていたとのこと。
噺に出てくる与太郎は若旦那の声限定のようですが、その気になれば何でも職業になる世の中だったようです。
その他の親子が対決する噺
-

-
落語 親子酒のあらすじ
落語 親子酒 いつも酒を飲みすぎてしまう商家の旦那と若旦那。酒を飲みすぎては失敗して後悔ばかりしている。さすがにこれではいけないと、親子ともども酒を断つことを誓う 数日後、若旦那が外回りに出かけたのを ...
続きを見る
-
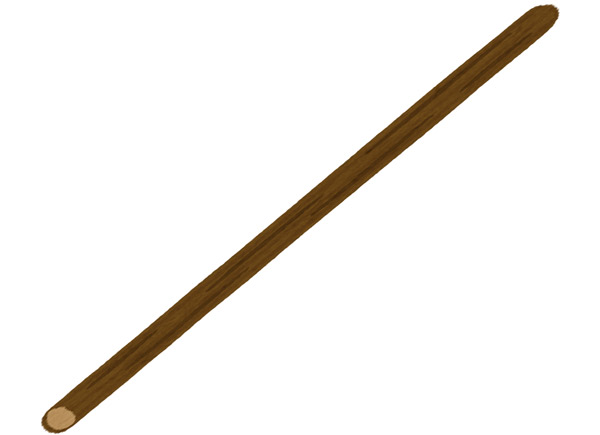
-
落語 六尺棒のあらすじ 江戸時代放火犯の末路とは
落語 六尺棒 道楽者で遊んでばかりいる大店の若旦那。今日も遅くまで飲んでしまい深夜に帰宅する。 こっそり家に入ろうとするが、しっかり戸締まりがしてあり中に入れない。 ドンドンドン 店の者に開けてもらお ...
続きを見る