落語 宗論
店が忙しいというのに若旦那が朝から姿を見せない。
番頭の話によると どうやら若旦那はキリスト教にかぶれて教会に入り浸っている様子。それを聞いた大旦那はカンカン
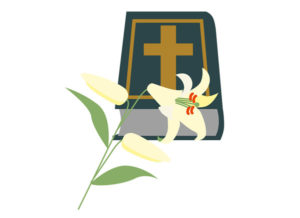
教会から戻ってきた若旦那に「うちは代々浄土真宗だ なぜ阿弥陀様に手を合わせない」と詰め寄るが
若旦那は
若旦那:
「阿弥陀如来に手を合わせるのは偶像崇拝であります。私の信ずるところの神は我々の造り主であります」

大旦那:
「おまえを作ったのは俺と死んだおまえの母親だ」
とうとう本気で怒った大旦那は若旦那の頭をポカり
騒ぎを聞きつけて止めに入ったのは使用人の権助
権助:
「旦那様 昔から宗論はどちらが勝っても釈迦の恥といいますだ。お釈迦様の恥は阿弥陀様の恥。どうぞ今日のところは私に免じてお収めくださいましな」
大旦那を諌めると
大旦那:
「よくそんなことを知ってるな。手を上げたのは私が悪かった勘弁しておくれ。だけど権助おまえの家も真宗だな?」
権助:
「あに?信州?おら仙台出身だから奥州だ」
釈迦の恥じと言われた宗論について
キリスト教が登場するということは禁教令が解かれた明治に入ってからの噺。登場する若旦那はお金を湯水の如く使ったり、怠け者だったりではなく、熱心に教会に通う珍しいタイプの若旦那。親を困らせるという点では同じですが^_^;
宗論はどちらが勝っても釈迦の恥 権助が大旦那をなだめた言葉は別に浄土真宗の教えではなく、江戸時代の川柳です。
宗派は違えど元々はお釈迦様の教えが元になっている仏教。優劣を競うこと自体が無意味なので、不毛な争いはするなということを諭し皮肉ったもの。
教義論争を宗論などと言ったりしますが、江戸時代以前には宗派どうしで頻繁にやりあったようで、負けると袈裟や法衣を剥ぎ取られたということもあったようです。
また、キリスト教と仏教宗派とが織田信長や豊臣秀吉の前で行ったという記録もあります。